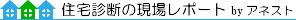大阪府の新築一戸建ての着工から完成までの検査の現場レポートです
住宅あんしん工程検査の現場レポート :大阪 Part1-2
こんにちは。代表の荒井です。前日の天気予報で、少し涼しくなるとの予報通り、秋らしい涼しさを感じつつ、朝から現場検査へ同行してきました。
担当の建築士と駅で待ち合わせして、車で拾ってもらい、現場へ。
鉄骨造3階建ての現場で地盤改良をしているところを確認に行ったのですが、工事が遅れており、まだ、その前の段階でした。残念。
この現場では、工事予定の確認をして、打ち合わせだけで終了して次の現場へ向かいます。
次の現場は、小規模住宅が密集する地域にある木造3階建て。こちらは、棟上が完了した時点でのチェックです。構造躯体(柱・梁・筋交い等)の検査です。

まずは、アンカーボルトやひねり金物などの金具類が正確に取り付けられているかを確認していきます。適切に取り付けられていることを確認し、全てOKが出ました!
「よしよし。」
ほかにも、火打ち梁やくも筋交いなども確認していきます。
建売住宅の場合、どうしても図面が完璧に揃っていないことが多く、現場の大工さんの判断に委ねられている範囲が多くなってしまっています。出来る限り、図面を用意し、その図面通りに工事を進めてもらうべきなのですが、現実にはそうなってないことが多い。残念なことですね。
図面に表示されてない金具などがあることが多いのですが、図面にはないが常識的に必要なものがあるかどうかもチェックしていきます。
例えば、かすがい、ひねり金物、ひら金物(短冊金物)です。

真ん中に金具が2つ並んでますが、左側が、ひねり金物で、右側が、かすがいです。
また、くも筋交いもそうです。

写真の右端の真ん中あたりから左へと伸びている木材が、くも筋交いです。
これらは、図面には表示されてないことが一般的です。さらに、なくても法的には問題のないものです。しかし、通常は、使用されるものです。図面になくても必要なものがあるかどうかも確認する。これも大事なチェック業務ですね。
さらに、構造用合板(床の下地)が、千鳥に(交互に)貼られているかもチェック。耐力上、交互に貼られる方が強いわけですね。(※一概にはいえません)

上の写真では、かえってわかりにくいですねぇ。(^^ゞ
墨で線を引いている箇所もあるので、余計に紛らわしいかもしれません。
「現在のところ、なかなかいい現場です。」と大和さん。
このまま順調に仕上がって欲しいですね。
一通りのチェックを終えた後、職人さんたちと打ち合わせ。工事内容の確認も行いますが、今後の工事の予定を確認し、次回の検査日程も決めます。


涼しい中の現場調査への同行でした。よかった。(^^ゞ
この日の移動中の車の中で、建築士さんと良い現場を見分けるコツについて話しました。それをご紹介しますと、
・大工さんがたる木をひざの上で切るような現場はダメ。
切れ目が斜めになってしまう恐れがあるし、目分量では寸法にずれが生じる
・台の上で寸法を測って切っている現場が良い。
木材に鉛筆で書き込みした跡があれば、寸法を測った証拠。これがあるかどうかは1つの判断材料になるとのことです。
注意して見てみましょう!
大阪府大阪市の着工から完成まで建築士が検査するサービスはこちら
担当の建築士と駅で待ち合わせして、車で拾ってもらい、現場へ。
鉄骨造3階建ての現場で地盤改良をしているところを確認に行ったのですが、工事が遅れており、まだ、その前の段階でした。残念。
この現場では、工事予定の確認をして、打ち合わせだけで終了して次の現場へ向かいます。
次の現場は、小規模住宅が密集する地域にある木造3階建て。こちらは、棟上が完了した時点でのチェックです。構造躯体(柱・梁・筋交い等)の検査です。

まずは、アンカーボルトやひねり金物などの金具類が正確に取り付けられているかを確認していきます。適切に取り付けられていることを確認し、全てOKが出ました!
「よしよし。」
ほかにも、火打ち梁やくも筋交いなども確認していきます。
建売住宅の場合、どうしても図面が完璧に揃っていないことが多く、現場の大工さんの判断に委ねられている範囲が多くなってしまっています。出来る限り、図面を用意し、その図面通りに工事を進めてもらうべきなのですが、現実にはそうなってないことが多い。残念なことですね。
図面に表示されてない金具などがあることが多いのですが、図面にはないが常識的に必要なものがあるかどうかもチェックしていきます。
例えば、かすがい、ひねり金物、ひら金物(短冊金物)です。

真ん中に金具が2つ並んでますが、左側が、ひねり金物で、右側が、かすがいです。
また、くも筋交いもそうです。

写真の右端の真ん中あたりから左へと伸びている木材が、くも筋交いです。
これらは、図面には表示されてないことが一般的です。さらに、なくても法的には問題のないものです。しかし、通常は、使用されるものです。図面になくても必要なものがあるかどうかも確認する。これも大事なチェック業務ですね。
さらに、構造用合板(床の下地)が、千鳥に(交互に)貼られているかもチェック。耐力上、交互に貼られる方が強いわけですね。(※一概にはいえません)

上の写真では、かえってわかりにくいですねぇ。(^^ゞ
墨で線を引いている箇所もあるので、余計に紛らわしいかもしれません。
「現在のところ、なかなかいい現場です。」と大和さん。
このまま順調に仕上がって欲しいですね。
一通りのチェックを終えた後、職人さんたちと打ち合わせ。工事内容の確認も行いますが、今後の工事の予定を確認し、次回の検査日程も決めます。


涼しい中の現場調査への同行でした。よかった。(^^ゞ
この日の移動中の車の中で、建築士さんと良い現場を見分けるコツについて話しました。それをご紹介しますと、
・大工さんがたる木をひざの上で切るような現場はダメ。
切れ目が斜めになってしまう恐れがあるし、目分量では寸法にずれが生じる
・台の上で寸法を測って切っている現場が良い。
木材に鉛筆で書き込みした跡があれば、寸法を測った証拠。これがあるかどうかは1つの判断材料になるとのことです。
注意して見てみましょう!
大阪府大阪市の着工から完成まで建築士が検査するサービスはこちら